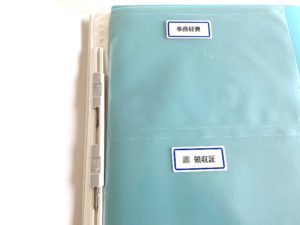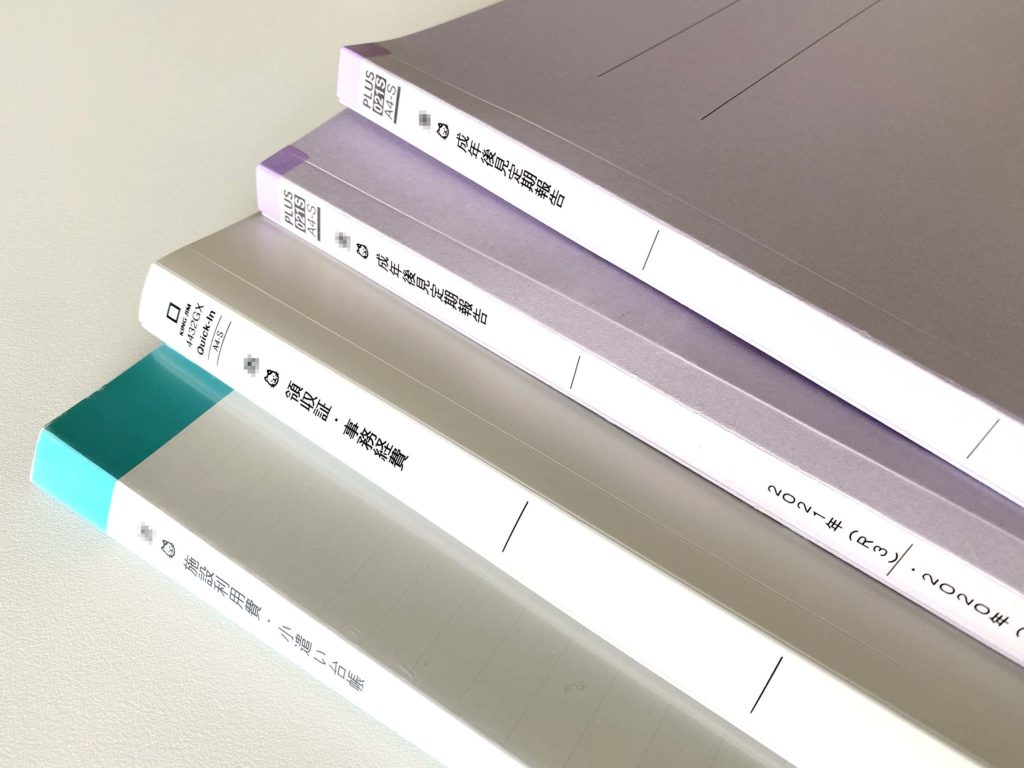こんにちは。
自分の事務所は、電子帳簿保存にしたので紙の領収証は破棄できるようになった姉ポです。
CdLSで最重度知的障がいをもつ妹の成年後見人をしています。
成年後見においては、まだ紙の領収証の保存が必要ですね。
姉ポの書類ファイルは減るのに、妹ちゃんの書類ファイルは増えるばかり。
管理や保存について、裁判所からの規定がないものは、
自分達に負担がかからないよう工夫したいもの。
今回は、日々の領収証や帳簿の管理、姉ポ流を紹介します。
もくじ
こまごま領収証が多い「生活用品費」は5ステップで処理
一番細々と領収証(またはレシート)が溜まるのは生活用品。
失くさないようにしないと自腹ですよね。
姉ポは【5ステップ】で処理しています。それぞれは次通り。
STEP1 まずは領収証袋にぶちこむだけ
出金発生ごとに記帳するのは処理の負担が大きすぎます。
領収証袋を作って未記帳の領収証を入れておきましょう。
ジップロックなどでもいいと思いますが、姉ポは、ポケットルーズリーフを使っています。
大事なのは、領収証を失くさないこと!
STEP2 エクセルの出納帳に入力する
エクセルの「現金及び預貯金出納帳」に入力していきます。
定期報告月には合計額が自動で計算されるのもエクセルのいいところ。
姉ポが作成したエクセルのシートは無料配布しています。
現金及び預貯金出納帳
-

-
【ダウンロードあり】後見業務、出納帳で金銭のながれを管理
成年後見事務で姉ポが利用している金銭管理の出納帳をダウンロードできるようにしました。日常で使われる口座が、現金と金融口座1つであれば、2つの出納帳で管理するよりもこの出納帳1つのほうがわかりやすいと思います。エクセルのデータです。
続きを見る
入力するのはある程度の枚数が溜まってから。または2ヶ月に1回ほどです。
小口現金
買い物は、全て姉ポが立て替えているので、現金残高がマイナスになることもあります。
つまり、現金マイナス分 = 姉ポの立替金額
マイナスもある程度の金額になったら、銀行口座から数万円を現金に移し、プラスにします。
入出金は日付順に入力します。
銀行口座の通帳を記帳してから、自動の入出金分と一緒にまとめて入力しています。
そうすると、入力した日の現金と銀行口座の残高がピシャリ!と合致します。
自動で入出金されるものは、次のようなものがあります。
記帳をしたときに、日付順で入力をしておきましょう。
出金:施設利用料、健康保険料
入金:障害年金、特別給付金等、工賃
STEP3 入力済み領収証にスタンプをペタる
入力済みと未入力の領収書を見わけるため入力が終わった領収証には印をつけます。
物理的に領収書等が混じってしまっても、確認の手間を省くことができるます。
現在妹ちゃん用に使っているのは、6mm角のOKマークです。
(PILOT FRIXION STAMP)
STEP4 台紙に貼り付ける
あとでファイリングをしたいので、
台紙は穴をあける手間が省けるルーズリーフを使ってます。
コピー用紙でもなんでもいいんです。
領収書は、定期報告で提出する必要はありませんが、家庭裁判所から求められた場合にはコピーのうえ提出します。
ですので家庭裁判所の規定に沿って作っておくとよいです。
福岡では次のとおり。
台紙サイズ:A4サイズ(横210mm縦297mm)
余 白 :左30mm
コピーをする時のために、領収証が重なって必要項目が見えないことがないように貼りましょう。
その時は右側に30mmの余白ができるわけですが、コピーの時にずらせば大丈夫!
STEP5 ファイリングしたら報告月まで放置する
台紙をファイルに綴じます。
姉ポは、2穴の紙ファイル(←プラスチック素材のものもあります)を使っています。
クリップ留めでもなんでもいいのですが、ちょうどいい使い勝手なので。
現行年度分1年分は「領収証・事務経費」に。
アクティブなファイルです。
このファイルの一番上には、さきほどの領収証保管につかうポケットルーズリーフがあります。
うちの場合は、施設利用料の請求書とお小遣い台帳は別ファイルに保存しています。
これらは2ヶ月に1回、入所施設から送られてくる帳票類なわけですが、ファイリングだけをします。
というのも、合算額が銀行口座から自動で引き落としされるため、帳簿への入力は記帳をしたタイミングに行うからです。
妹ちゃんがいる入居施設では、施設利用費の書類を2ヶ月に1回まとめてくださいます。
- 直近2ヶ月分の施設利用の請求書
- お小遣いで買った食べ物や生活消耗品などの領収証
- 医療にかかった費用の領収証
- 3ヶ月前と4ヶ月前の施設利用領収証
報告月をすぎたら
定期報告が終わったら、報告済み書類として別のファイル「成年後見定期報告」に移しています。
保管用のファイルです。
領収証のない「交通費」は出金伝票で処理
領収証をもらうことが可能なタクシー代、新幹線などの長距離の電車代は領収証を保管。
しかしバス代や近距離の電車代は領収証がありませんので、手書きの出金伝票で管理しています。
出金伝票の記載項目は次のとおり。
- 日付
- 行動先(「施設名」「○○役所」「○○銀行」など)
- 品目(「電車代」「バス代」+「何の用事で移動したか」)
- 金額
郵便代(切手・レターパック)のストックも出金伝票で処理
切手やレターパックなどは、書類発送が生じた都度、購入に行くことはまずないでしょう。
まとめて購入して、本人用を別管理できればいいのでしょうが、姉ポは難しいです。
便利なレターパック
プラス(赤)とライト(青)それぞれに、仕事用、姉ポ用、妹ちゃん用って、どれが在庫薄なのかの管理があるし、結構な枚数よ!
料金バラバラな切手
かさばらないけど種類が多すぎ!
シートで買っていると、郵便料金の改定で2円とか別に貼らなくちゃいけなくなるし。
手間を省くためにせっかくシールタイプの切手を買っていても、端数の切手はのりで貼らなくちゃいけないイライラ。
なので、こまごましたものは、姉ポの在庫分から分けるようにしています。
(税務申告ではないので)大事なのは、本人のために「何」を「何のために」「いくら使ったか」を証明すること。
都度領収証がないので、交通費同様に手書きの出金伝票を利用しています。
出金伝票の記載項目は次のとおり。
- 日付
- 行動先(=発送先「施設名」「○○役所」など)
- 品目(「切手」「レターパック」+「何を発送したか」)
- 金額
処理手順は次の流れです。
- 使う金額の切手などを、姉ポから分けてもらう
- 現金を払う(妹ちゃんの現金 → 姉ポ)
- 出金伝票を書いて領収証袋へ
「後見事務経費」には用途や行動先を記録しておくこと
後見事務経費の領収証は、別に保管し「後見事務経費」としています。
帳簿つけの手順は本人同様5ステップです。
領収証袋にぶちこむ
経費帳に入力する(エクセル)
入力済み領収証にOKスタンプをペタる
台紙に貼る
ファイリング
紙ファイルは、妹ちゃんのものと同じアクティブファイルを使っています。
現行年度分1年分の「領収証・事務経費」です。
インデックスを使い、本人の入出金とは別に管理しています。
領収証を受け取ったらすぐに、何に使った経費かわかるよう領収証のはしっこや裏にメモしておくといいです。
例えばコピー代。
「どこに提出する、何の書類を」など。
郵送代も同様。
「どこに、何を送ったか」など。
後見事務の出金分は、エクセルの「経費帳」に次の項目を入力。
- 日付
- 摘要(「切手」「レターパック」「交通費」など)
- 行動先(「施設名」「○○役所」「○○銀行」など)
- 金額
- 備考(「○○申込書」「支援計画」「証明書」など)
経費は妹ちゃんの現金から出します。
現金が不足の時は、姉ポが立て替えてあとで清算。
清算分は「現金及び預貯金出納帳」に入力します。
まとめ
この記事では次の領収証について、姉ポの処理のしかたを紹介しました。
- 生活用品費
- 交通費
- 切手・レターパック代
- 施設利用料
- 後見事務経費
姉ポが管理を始めてから4年ほど経ちます。
今の環境が変わらなければ、このやり方が安定しているので続けます。
姉ポは、金融機関のクラークとしてファイリングなどを行なっていましたし、自身の事業で20年以上のあいだ経理をやっています。楽をしながら間違えなく管理するために、常により良い方法を考えています。
姉ポのやり方がどなたかの参考になりますと幸いです。
同居家族の方へ
妹ちゃんは離れて施設入居をしていますが、本人と同居されてる方は、生活費の按分もあり私どもとは比べものにならないほど複雑であるとお察しします!
SMBCの後見サービス(←開発時に姉ポも協力をしました)の利用などで、正確かつ比較的楽に管理できます。
とはいえ、まだ東京家庭裁判所以外の地域には対応できていない様子です。
今後もより良いやりかたやサービスが見つかれば、記事にしていくようにします。