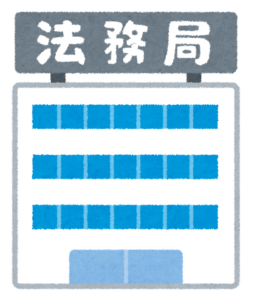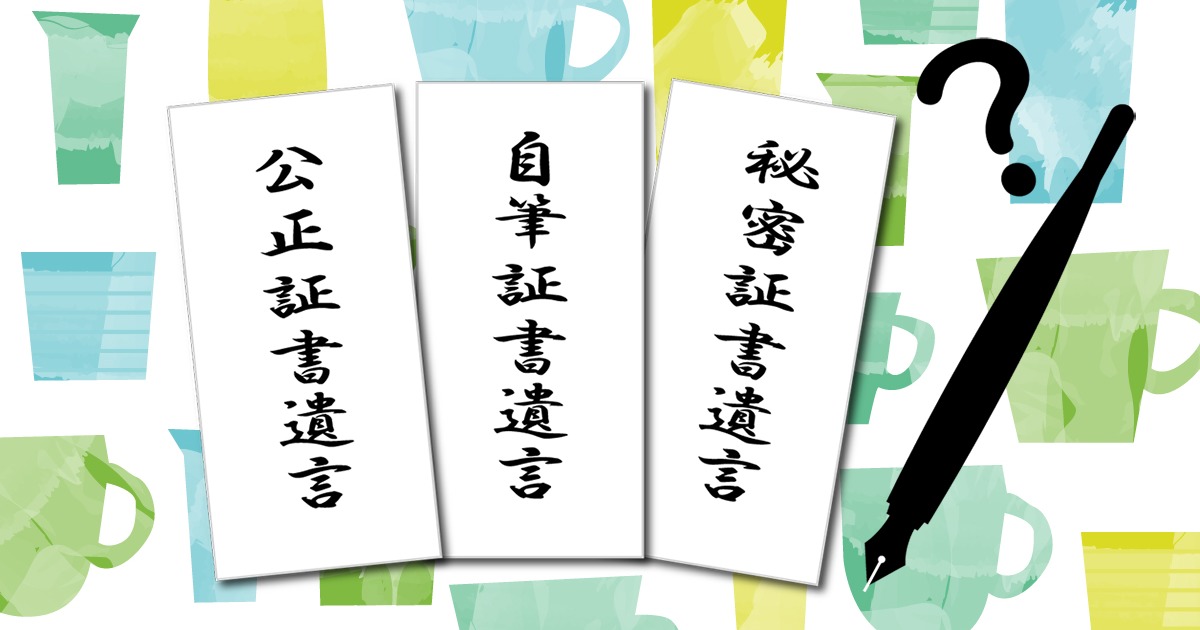
知的障がい者のご家族に問う!ご自身が亡くなったあとの財産は法定相続で大丈夫でしょうか。知的障がい者に必要以上の財産を残すと、意に反して職業後見人がつけられたり面倒なことも起こり得ます。財産分与を検討し(相続税も考えながら)遺言書を作成しておくのもいいかもしれません。
遺言に関わる書籍も装丁してきました姉ポです。
CdLSで最重度知的障がいをもつ妹の成年後見人をしています。
◆ ◆ ◆
令和2年7月10日。
法務局において『自筆証書遺言書』の保管ができるようになりました。
これを自筆証書遺言書保管制度といいますが、姉ポは利用しやすい制度ができたなと思いました。
祖父母、両親が立て続けに亡くなり、本人らの意思を明確にしておいてくれたらよかったのにと思うこともありましたので、自身この制度を利用して遺言書を保管しておこうと考えています。
◆ ◆ ◆
利用にあたり色々調べたので、備忘録にしておきます。
この記事では、どんなものかざっくり知りたい人に役立つよう1ページにまとめました。
まず自筆証書遺言書と公正証書遺言のちがいを整理します。
次に、自筆証書遺言書保管制度の利用のしかたや注意点などを解説します。
もくじ
遺言書とは
まず遺言書とは、亡くなったのち遺族へ自身の望みを伝える書面です。
遺言書には、残した財産で遺族が争うことがないよう、財産分割与や遺産管理の指示を明確に記しておくことができます。
遺族へのメッセージも書くことができます。
遺言書の種類
遺言書には次のような種類があります
- 自筆証書遺言書 : 遺言者が自身で書くもの。
- 公正証書遺言書 : 公証人と証人の前で作成されるもの。
- 秘密証書遺言書 : 遺言者が自身で書き、公証人と証人によって遺言書の存在のみを証明するもの。内容は遺言執行者以外には秘密にされる。
ほか。
法律上要求される特定の形式を持つ特別な形式の遺言書(例えば、軍人の戦時遺言書など)、瀕死の状態で証人の前で口述され、記録される口述遺言もあります。
自筆証書と公正証書の違い
特に財産や相続人が多い場合などは公正証書を利用するのがよいかと思います。
公正証書は、本人の意思を聴取し公証人が作成するため書類の不備への心配はありません。
しかし自筆証書や秘密証書では、自身で書類を作成するため、万一不備があった場合にその遺言書は無効となってしまいます。
また偽造を防ぐため遺言書に封をしますが、開封するには家庭裁判所の検認が必要です。
| 遺言書 | 作成者 | 内容の証人 | 存在の証人 | 保管場所 | 開封時の検認 |
| 自筆証書 | 本人 | なし | なし | 本人 | 必要 |
| 秘密証書 |
あり |
||||
| 公正証書 | 公証人 | あり | 原本を公証役場 写しを本人 |
必要なし |
検認
遺言書の偽造や変造を防止するための手続です。遺言書の有効・無効を判断するための手続ではなく、検認の手続を経ずに開封した場合でも、遺言自体は無効とはなりません。5万円以下の過料に処せられます。
姉ポは必要ないと思うけどね〜
自筆証書遺言書保管制度とは
自筆証書遺言書を法務局で保管する制度です。これにより、開封時に家庭裁判所の検認が必要なくなります。
| 自筆証書遺言保管制度 | 作成者 | 内容の証人 | 存在の証人 | 保管場所 | 開封時の検認 |
| 利用なし | 本人 | なし | なし | 本人 | 必要 |
| 利用あり | あり | 法務局 | 必要なし |
こちらのリンクにわかりやすい図解が掲載されています。
実際に保管申請される場合はこちらにそって準備することをお勧めします!
自筆証書遺言書保管制度利用のメリット
公正証書遺言書は、証人2人を連れ公証役場へ出向き(公証人が出向いてくれることもある)、数万円の費用(内容により増減)をかけて作成します。
自筆証書遺言書は自身で作成することができ手軽ではあるが、その存在の不明確さや開封時の手間がかかってしまうデメリットも。
自筆証書遺言書保管制度を利用することよって、確実に保管でき、開封時の検認の手間もなくなるので遺言書作成のハードルが下がりますね。
また、保管期間中に遺言書の閲覧、遺言書情報証明書や遺言書保管事実証明書の交付を受けることもできるのもメリットといえます。
姉ポが考える自筆証書遺言書保管制度利用のメリットは次の通りです。
- 本人の意思を相続人に伝えられる。
- 偽造の心配がなく保管される。
- 自分だけで手続きが行える。保管内容の確認や撤回ができる。
- 安い。1通3,900円
自筆証書遺言書を作成する
自筆証書遺言書保管制度を利用するには、まず自筆証書遺言書を作成しましょう。
作成には民法上の要件を満たす必要があります。また、保管にあたっての様式やルールがあり注意点は次の通りです。
- A4サイズの紙に、自書で遺言内容、作成日と氏名を書き、押印する。
・作成日は日付を特定できるよう明確に。
・周囲の余白部分には何も記載しない。
・余白は、A4縦位置で左20mm以上、下10mm以上、上と右に5mm以上。 - 財産目録についてはパソコンで作成・印刷したものや、通帳の写しでもOK。
・不動産は登記事項証明書の添付でもOK。
・財産目録の全てのページに署名と押印が必要。 - 訂正や追加をした場合は、その箇所がわかるようにする。
・訂正・追加箇所とその旨を明記、その箇所に署名と押印が必要。
法務局に保管の申請をする
保管する法務局を決めたら、必要書類を準備し、保管申請の予約を取ったうえで法務局に来庁します。
保管する法務局を決める
- 遺言者の住所地を管轄する遺言書保管所
- 遺言者の本籍地を管轄する遺言書保管所
- 遺言者が所有する不動産の所在地を管轄する遺言書保管所
必要書類の準備
1:遺言書
- 複数枚の場合にもホチキスやクリップで止めたりせずバラバラのままで。
- 封筒に入れない。
2:遺言書の保管申請書
来庁前に必ず記入する必要があります。
(記入がなかった場合、再度予約・来庁になる場合も)
- 遺言書の保管の申請書様式PDF
- 継続用紙PDF(申請書の受遺者等・遺言執行者等欄が足りない場合に添付)
- 記入例・注意事項PDF
3:住民票の写し
- 作成後3か月以内のもの
- 本籍及び筆頭者の記載入り
- マイナンバーや住民票コードの記載はなし
4:顔写真付きの身分証明書(マイナンバーカードや運転免許書など)
5:3,900円分の収入印紙(手数料)
法務局内の収入印紙販売窓口や郵便局にて販売しています。
来庁予約をする
遺言書を保管をする法務局で手続きをしますが、来庁には予約が必須となります。
予約方法は、オンラインと電話の2つがあります。HPで猛烈にオンラインを勧めており実際便利です。
予約に関する注意事項
- 遺言書保管に関する手続きには、受付から完了までに約1時間を要します。
- 予約は手続きをする本人が行い、本人名を登録します。予約は1名につき1枠(1時間20分)が必要です。
予約可能な期間
- 30日先まで予約可能
- 午前中は、翌業務日以降の予約が可能
- 午後は、翌々業務日以降の予約が可能
- 当日の予約は不可
オンライン予約
法務局手続案内予約サービスの専用HPで予約
24時間365日(メンテナンス時除く)利用可能
予約日時の変更をHPで行うことができます。ただし、当日のキャンセルなどについては、予約をした法務局(遺言書保管所)へ直接電話連絡をします。
- 手続きを行う法務局を選択
- 「予約手続き」の「手続き一覧」から該当法務局の遺言書保管手続予約を選択
- 「予約申込に関する事項」を読み「同意する」にチェック
- 予約可能日「○」から希望日を選択
- 予約可能時間「○」から希望の時間を選択し「予約する」ボタンをクリック
- 案内に従い情報を入力してください
電話予約
手続きをする法務局(遺言書保管所)へ電話番号をして、予約可能日時を確認のうえ予約
平日8:30~17:15(土日祝日、年末年始を除く)
法務局(遺言書保管所)へ来庁する
- 必要書類を持って、受付開始時刻までに窓口に行きます。(予約した時間内ではなく開始時刻までに行きます)
開始時刻から10分遅刻すると、予約がキャンセルされる場合があります。 - 指示に従って書類を提出します。
- 申請書類に問題がなく手数料の納付も行えば手続終了です。
手続が無事に終了すると、保管証を渡されます。
要注意
保管証は,再発行ができないので紛失しないようにしてください。
相続人に保管証の写しを渡しておくか、保管した法務局と保管番号を伝えておくのが安心です。
まとめ
- 遺言書には、自筆証書遺言書、秘密証書遺言書、公正証書遺言書がある。
- 自筆証書遺言書保管制度とは、自筆証書遺言書を法務局に保管できる制度である。
- 制度利用のメリットは、手軽に安く確実に遺言を残せること。
- 保管手続き終了後に渡される保管証はなくさないこと。
自筆証書遺言書保管制度は、確実に遺言を残せる方法のひとつとして手軽に利用できることがわかりました。
遺言の準備が、障がい者家族の将来を考えるきっかけになるかもしれませんね。
「兄弟なかよく支えあってね」とか。